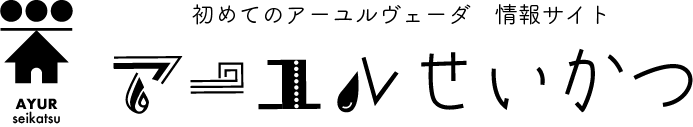アーユルヴェーダの初冬の過ごし方

初冬とは
アーユルヴェーダでは冬は「初冬(へーマンタ)」と「厳冬(シシラ)」に分けられます。
初冬とは、立冬の11月上旬から始まり12月にかけて寒さが増していく季節のことで、冬の前半をいいます。
一年で最も消化力と体力が高まり、運動に最適な時期といわれています。良質で高カロリーな食事をすることで健康を維持できますので、この時期のダイエットは体の不調につながりやすいので注意しましょう。
この時期は、冷たい風が吹き始め、空気が乾燥する傾向があります。
太陽が降り注ぐ時間も短くなり、活動時間が減少することにより、自然とエネルギーが低下しがちです。
また、気温が下がることで血行が悪くなり、筋肉がこわばりやすくなるため、体を温めることが重要です。
初冬のドーシャの傾向
初冬は「ヴァータ(風)」と「カパ(水)」のドーシャが優勢になる季節です。
特にヴァータが優勢になるため、皮膚や髪の乾燥、乾燥した咳、冷え、体のこわばり、心の不安などが増える傾向があります。
また、寒くなるにつれて、身体の冷性や緩慢性が増えるため、カパのエネルギーが優勢となり、重さやだるさ、浮腫を感じやすくなります。
一方、秋に増えたピッタは、寒さにより鎮静していきます。
初冬によくある症状
初冬に多くみられる症状は、ヴァータやカパの影響が大きいです。
初冬は、肌や髪が乾燥し、かさつきが気になることが多くあります。口や鼻の粘膜も乾燥しやすく、風邪の原因にもなります。
寒くなるにつれて、手足の末端が冷たくなり、血行不良によりむくみが起こることがあります。
また、一層寒さが厳しくなりカパが増加し始めると、朝が起きにくい、体が重いといった倦怠感が増えることも。
体と心の不調
乾燥に伴う症状が見られやすい
- 肌や髪の乾燥
- 風邪をひきやすい
- 血行不良
- むくみ
- 手足の冷え
- 不安感
- ストレス
- 倦怠感


初冬に取り入れたい生活処方
この時期は、体を温め、乾燥を避け、心を落ち着かせることが重要です。初冬に効果的なアーユルヴェーダの健康対策を紹介します。
METHOD
01
体をとにかく温める
北風が冷たくなりますので、白湯や生姜入りのハーブティーやスパイスティーで体の内側から温めましょう。
そして風邪をひきやすい時期ですので、衣服は重ね着で、温度調整できるようにする良いでしょう。
なるべくオイルマッサージを行い、マッサージした後はゆっくり湯船に浸かり、体の芯から温まることが大切です。

METHOD
02
潤い対策を万全に
髪や肌、喉、目など全身が乾燥していきますので、保湿をすることが重要です。特に口や鼻の粘膜が乾燥しやすく、風邪をひきやすくなっていますので、部屋は加湿をするなど対策をしておきましょう。
太白ゴマ油を使ったセルフマッサージ(アビヤンガ)は、ぜひ行ってください。忙しい時は三点マッサージをするだけでも効果があります。皮膚の抵抗力が増進します。
料理の油脂類はギー(バターオイル)を使うと良いでしょう。

METHOD
03
消化力が強いので食事を大切に
高カロリーのもの、乳製品、揚げ物、新米など消化に重いものでも消化できる季節です。栄養の吸収力も強くなりますので、身体に適した旬の食材をとると良いでしょう。
免疫力向上に最適な時期です。
この時期はヴァータを鎮静させる甘味・酸味・塩味を少し多くとるようにしましょう。

METHOD
04
心をリラックスさせること
日照時間が短くなることでセロトニンの分泌量が減り、うつ症状がみられやすいといわれています。ヴァータやカパが優勢なることで、不安感や倦怠感を感じやすくなりますので、なるべく朝日を浴びたり、体を動かしたりして気分をリフレッシュさせましょう。
規則正しい生活を心がけることで、精神的にも安定します。

CAUTION
!
避けるべき初冬の生活処方
辛味・苦味・渋味、冷性はなるべく控えましょう。
この時期に消化に軽いものを食べるとヴァータを悪化させますので注意しましょう。
横になって昼寝をすることで体調不良になりやすいので、気をつけましょう。
寒い風にさらされたり、月光を浴びることは初冬は避けるべきです。
初冬に取り入れたい
食材・スパイス
初冬は滋養のあるものを充分に食べることが大切です。
ヴァータを鎮静するような食材やスパイスを取り入れたいですね。
甘味・酸味・塩味、温性・油性のあるものをとって、ヴァータを鎮静させましょう。
具体的な料理をあげると、お肉や野菜の鍋、温性のスパイスを入れた野菜の炒め物など、温かくスパイスを取り入れた食事がお勧めです。
● ● ●
参考文献
日本アーユルヴェーダ学会・訳. チャラカ本集総論篇. 3版, せせらぎ出版, 2019, 767p, p.122-124
クリシュナ・U・K. 古典から学ぶアーユルヴェーダ. 東方出版, 2019, p214, p.83-88