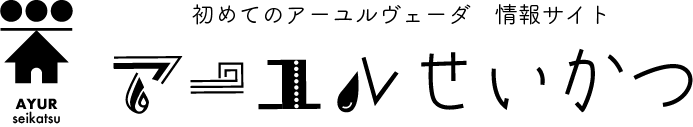日本でとりたい
アーユル食材

健康に役立つ食材の力で
まいにち元気に
日本の食卓でぜひ取り入れて欲しいアーユルヴェーダな食材を紹介します。
日本で購入できる食材を中心にアーユルヴェーダに関する文献を参考に内容をまとめてみました。
健康に過ごすための予防対策として、参考にしていただけましたら幸いです。
ただし、体調不良の際はセルフケアに頼りすぎず、必ず早めに医師の診察を受けてください。

生姜 |ショウガ
Ginger
- 野菜
- 乾燥
- 粉末
主な作用
万能薬といわれ、
味覚をよくし、消化力を促進
あらゆる組織に作用し、消化器系や呼吸器系に生姜を用いることは有名。生の搾り汁はヴァータやカパの不調、便秘などの効果もあります。

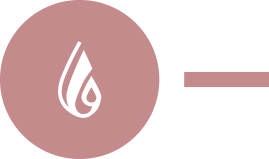

特性
生姜は生から乾燥したものまで様々な料理に使われる食材です。
属性(グナ):(生)重性・乾性・鋭性
(乾燥)軽性・油性
味(ラサ):辛味
効力(ヴィールヤ):温性
消化後の味(ヴィパーカ):(生)辛味
(乾燥)甘味
健康ポイント
生ショウガを多量にとると消化に負担がかかるので、細かく切ったり、すりおろしをしたりして色々な料理に少しずつ使うことをお勧めします。夏の新生姜は夏バテや消化不良の予防になります。冬の辛味の強い生姜は食欲を増進させます。

緑豆 |ムング豆
Mung beans
- 乾燥(皮つき・なし)
主な作用
豆類の中で最も有益なもの
一般的に春雨や豆もやしの原料になっている豆です。
とても消化しやすい豆で、米に比べてタンパク質や食物繊維、ビタミンB1・B2、カルシウムなど豊富に含んだ食材です。



特性
ムング豆ごはんやムング豆お味噌汁など和食の料理にも合う食材です。
属性(グナ):乾性・冷性・軽性・清澄性
味(ラサ):渋味・甘味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
緑豆は乾性なので、油分やスパイスと一緒にとると良いでしょう。皮なしのイエロームング豆をお粥にした「キチャリ」は、消化に軽いため、体調不良や断食明けなどに最適です。

冬瓜
Winter melon
- 野菜
主な作用
利尿作用に優れていて、むくみ改善に
腎臓で老廃物を排出する作用からむくみの解消や高血圧に効果があります。ビタミンCも豊富なので、肌の健康維持にも役立ちます。


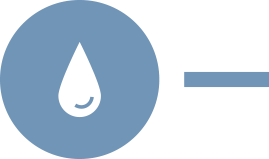
特性
カロリーが低く、食物繊維が多く含む野菜のため、ダイエットにも役立ちます。
属性(グナ):軽性・油性
味(ラサ):甘味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
特殊作用(プラヴァーバ):知力を良くする
健康ポイント
ウリ科の野菜で、夏に採れて冬まで保存できる食材で、皮から種まで全て食べられる大変重宝する食材です。カットせずに、丸ごと実のまま保存しておき、冬にも冬瓜料理を楽しみましょう。

アムラ|アーマラキー
Amla
- 果実
- 乾燥
- 粉末
- サプリメント
主な作用
ビタミンCが豊富なアーユルヴェーダ食材
生の果実は日本ではインド食材店でしか見かけないアムラ。3つのドーシャを鎮静させるスーパーフードです。優れた強壮剤で若返り、呼吸困難、眼病、皮膚病、解熱、鎮痛など様々な作用があります。



特性
有益な果実(トリファラ)の一つとされています。
属性(グナ):軽性・乾性・冷性
味(ラサ):甘味・酸味・苦味・辛味・渋味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
特にピッタの鎮静に効果があります。馴染みのない食材なので、まずはアムラキャンディーやサプリメントなどで試してみましょう。

ぶどう
Grape
- 果実
- 乾燥
主な作用
適度に体を冷やし、滋養効果に優れた果物
喉の渇きや灼熱感を抑えてくれます。
心臓を丈夫にし、血液組織に良い。脳の働きを良くし、精神を落ち着かせる。呼吸困難や咳にも良い、滋養強壮、整腸作用など様々な効果がある果物です。


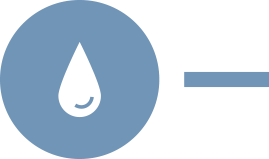
特性
アーユルヴェーダの果物といえば「黒いぶどう」。
緑や赤いぶどうもありますが、甘味と酸味のバランスがよく、ポリフェノールが多く含まれた黒いぶどうが良いといわれています。
属性(グナ):油性・滑性
味(ラサ):甘味・酸味・渋味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
果物は熟した果実を食べることが大切です。ぶどうは大人は1日に10〜15粒、子どもは5粒を目安に食べましょう。また、干しぶどう(レーズン)の健康に良いので、ぜひ日々の生活に取り入れてみましょう。

かつお節
Benito
- 削り節
- 粉末
主な作用
生活習慣病の予防に最適な食材
鰹節には血液をサラサラにし中性脂肪やコレステロールを下げる働きがあります。また肥満予防や血圧調整など役立つ作用があります。



特性
海水魚は体力を与え、滋養する効果があるため、乾燥させることで軽性となり、少量を毎日とることは健康に良さそうです。
属性(グナ):軽性・乾性
味(ラサ):甘味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
注1:上記特性はアーユルせいかつの考察です
健康ポイント
そのまま食べるのはもちろん、昆布などの合わせだしで食材の良さを引き立てながら味わうのがお勧めです。出汁を取ると、六味(甘味・酸味・塩味・苦味・辛味・渋味)をとることができるといわれているので、日本の食卓には欠かせないものです。

梅
Ume
- 果実
- 乾燥
主な作用
疲労回復や食欲増進のために梅干しを
梅には身体に必要なミネラルが豊富に含まれてます。疲労回復、殺菌作用、食欲増進、消化促進、肥満、免疫力アップ、抗アレルギー効果など様々な効果があるので、日本人には欠かせない食材です。
【青梅】



【完熟梅】



特性
青梅と完熟梅では特性は異なりますが、どちらも酸味が強いのが特徴です。
【青梅】
属性(グナ):重性・乾性・鋭性
味(ラサ):酸味・渋味・苦味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):酸味
【完熟梅】
属性(グナ):重性・乾性
味(ラサ):酸味・甘味
効力(ヴィールヤ):温性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
昔から青梅は梅ジュースや梅酒、完熟梅は梅干しに使われています。特に梅干しは日本人が慣れ親しんだ味。そのまま食べるだけでなく、料理にちょこっと加えることで体も心も喜びますよ。
青梅は生食厳禁です!梅は必ず加工して食べましょう。

キャベツ
Cabbage
- 野菜
主な作用
胃腸を丈夫にするビタミンU(キャベジン)が豊富な野菜
ビタミンCやタンパク質が比較的多く含まれ、食物繊維も豊富です。特にピッタに良い野菜といわれています。便秘軽減、イライラ解消、皮膚病、アトピー、免疫を強化などの作用があります。



特性
頭が熱っぽい時にキャベツの一番外の葉を帽子にするとひんやりして気持ち良いので、ぜひ試してみては。
属性(グナ):粗性・乾性
味(ラサ):甘味・渋味・苦味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):辛味
健康ポイント
春キャベツは巻きが緩く、柔らかいので、アーユルヴェーダでは、さっと茹でて食べるのがおすすめです。秋に出る冬キャベツは巻きが密集して味が良く、煮込み料理向きです。冬に出回る芽キャベツ(キャベツを品種改良したもの)は小さいながらも栄養素がキャベツの数倍含まれています。

アスパラガス
Asparagus
- 野菜
主な作用
生理痛の緩和など婦人科系のトラブルに
穂先にはオージャス(生命力の源)が詰まっていて、3ドーシャを整える効果があります。疲労回復、免疫力、滋養効果が高い。老化防止、認知症予防、血液浄化、美肌、利尿作用など様々な作用があります。特に婦人科系の不調に勧められる野菜です。



特性
同じ属性で根っこはシャタワリといわれ、若返りのハーブとして重宝されています。
属性(グナ):重性・油性
味(ラサ):甘味・苦味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
色々な効果が期待されているので化粧品や医薬品などにも使われていて、研究も進んでいます。3ドーシャに良いのでぜひ積極的に食べたい野菜です。

たけのこ
Bambooshoot
- 野菜
主な作用
鼻水や咳、だるさなど春特有の不調におすすめ
花粉症のアレルギー症状や眠気など、カパの不調に役立つ食材。春先は心が不安になりやすいので、不安、不眠、乾燥、体の痛みがある方は食べ過ぎには注意しましょう。

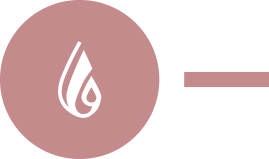

特性
薬効は穂先に強く出やすいといわれています。たけのこはしっかりアク抜きをしてから料理に使いましょう。
属性(グナ):重性・冷性・微細性
味(ラサ):渋味・苦味・甘味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):辛味
健康ポイント
部位で味わいや歯応えが違いますので、部位ごとに調理法を変えて食感も楽しみましょう。甘味を加えたたけのこご飯は、筍の新鮮な香りを楽しみつつ、心も体も健康になれる献立です。

とうもろこし・ヤングコーン
Corn・Young Corn
- 穀物
- 野菜
主な作用
甘味が豊富で高い栄養価をもつ夏の食材
タンパク質、脂質、ビタミンがバランスよく含み、糖質が豊富なとうもろこし。夏に甘味をとるのに最適。またヤングコーンは、カロリーや糖質が少ないのに栄養素たっぷりなので、ダイエットには嬉しい食材です。



特性
鮮度が落ちるのが早いので、買ったらその日のうちに食べると身体への効果も期待できます。
属性(グナ):軽性・粗性
味(ラサ):甘味
効力(ヴィールヤ):温性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
ヤングコーンのひげは、健康に良い上に美味しいので、ぜひ食べてほしいです。とうもろこしの芯は栄養たっぷりなので出汁に使えます。

枝豆
Edamame
- 野菜
主な作用
疲労回復や肌トラブルをサポート
ビタミンB1は消化液の分泌を促し、糖質や脂質を分解してエネルギーに。さらにメラニンの抑制や肌細胞を活発にしてくれるビタミンCが豊富なので、紫外線の強い時期には最適。抗酸化作用もなり、「お肌の万能薬」ともいわれます。



特性
「畑の肉」といわれ、良質なタンパク質を豊富に含んんでいます。
属性(グナ):冷性・重性・乾性
味(ラサ):甘味・渋味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
おつまみの定番の枝豆は、他の野菜に比べて高カロリーなので、食べすぎると太る原因に。また、プリン体が多く含まれるため、食べすぎは痛風になるリスクになるので、ほどほどに。

そら豆
Fava beans
- 野菜
主な作用
疲労物質をデトックスする滋養食材
植物性タンパク質に富、ビタミンB1、B2が豊富に含まれています。疲労回復や美肌効果、むくみ解消など梅雨時期には欠かせない食材。食物繊維も多いため、お腹の調子を整えます。



特性
鮮度が落ちるのが早いので、買ったらその日のうちに食べましょう。
属性(グナ):冷性・重性・乾性
味(ラサ):甘味・渋味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
そのままグリルしたり、さやから取り出した豆を少量の岩塩を加えた熱湯で茹でたりして素材そのものを楽しみましょう。豆類はガスが溜まりやすいので、ヒングやクミンと一緒にとると良いです。

実山椒
Japanease long pepper
- 野菜
主な作用
胃腸の調子を整える刺激的な食材
ビタミン類やミネラルが豊富に含まれている実山椒。基礎代謝の向上や内臓の働きを活発にする作用があります。辛味成分は消化機能の働きを促進します。



特性
属性(グナ):軽性・鋭性
味(ラサ):辛味
効力(ヴィールヤ):温性
消化後の味(ヴィパーカ):辛味
注1:上記特性はアーユルせいかつの考察です
健康ポイント
とれたての実山椒は、香りも良く、下ごしらえしてから料理に使いましょう。冷凍保存しておくと青い味の状態のまま保存できます。

ゴーヤ
Bitter melon
- 野菜
主な作用
夏バテや食欲不振の予防のために食べたい
胃腸を刺激して食欲を増進させる効果があるモモルデシンが含まれていることから夏バテを改善する効果があります。
日焼け対策や免疫力を高めるビタミンC、赤血球を作る葉酸、強い抗酸化作用をもつビタミンE、血圧を下げるカリウムなど栄養価の高い野菜のひとつ。



特性
苦味や渋味は、オイルやスパイスと一緒にとると食べやすくなります。
属性(グナ):冷性・粗性
味(ラサ):苦味・渋味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):辛味
注1:上記特性はアーユルせいかつの考察です
健康ポイント
ワタや種は果肉の3倍以上のビタミンCがあるといわれているので、捨てずに全部食べましょう。

きゅうり
Cucumber
- 野菜
主な作用
美肌×腸活に欠かせない低カロリー食材
カリウムが多く含まれているため、塩分量を調整する利尿作用があるため、むくみ予防につながります。
ビタミンCや不溶性食物繊維が多く含まれ、美肌効果や腸内環境の改善が期待できます。


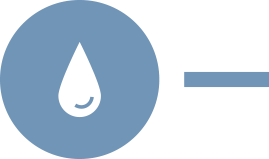
特性
重性なので、消化力が低下している時は、丸ごと食べずに、少し加熱したり、細かく切ったりして工夫しましょう。
属性(グナ):冷性・重性・流動性
味(ラサ):渋味・甘味・酸味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
低カロリーなのに栄養価が高いので、夏の暑い日に食べることで水分補給になります。また空腹感を満足させるのでダイエット効果もあります。

スイカ
Watermelon
- 果物
主な作用
水分補給&健康に良いこといっぱいの夏の食材
約90%は水分でできているスイカは、糖質やビタミン、ミネラルをはじめ、アミノ酸の一種のシトルリンが含まれており、血流を改善する効果が期待できます。β-カロテンが豊富に含まれ、老化防止や疾患予防に役立ちます。トマトと同じくリコピンが多く含まれており、トマトに比べて1.5倍と非常に高いです。



特性
冷性で体をクールダウンするのに最適です。
属性(グナ):重性
味(ラサ):甘味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
スイカと天ぷらの食べ合わせは良くないといわれています。身体を冷ます作用と温める作用の組み合わせですので、避けましょう。
オクラ
Okra
- 野菜
主な作用
オクラのネバネバには栄養素がいっぱい
オクラは脂質よりタンパク質と炭水化物の割合が高い低カロリー野菜です。カルシウム、カリウム、食物繊維のほか、βカロテンやビタミンK、葉酸などの栄養が豊富な緑黄色野菜のオクラ。
夏バテ防止や免疫力アップ、美肌効果や身体の老化防止などの効果が期待できます。



特性
アーユルヴェーダでは、地産地消の食材を勧めていますので、6~9月の旬な時期に収穫された新鮮なオクラを食したいですね。
属性(グナ):粗性
味(ラサ):甘味・渋味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):辛味
健康ポイント
βカロテンやビタミンKの脂溶性ビタミンは、油と一緒に調理することで吸収力が高まるので、スパイスと一緒に炒めるのも良いでしょう。
茹で過ぎないようにサッと40秒ほど湯通ししてからカットすると豊富な栄養素の流出を防げます。

ジャガイモ
Potato
- 野菜
主な作用
でんぷん、ビタミンC、カリウムが豊富な栄養補給食材
ジャガイモの葉や茎が日光をたくさんあびて育ったジャガイモは、でんぷんやビタミンCが豊富です。じゃがいもにはペクチンという食物繊維が含まれており、腸内環境と整えて排便をスムーズにする作用があります。
カリウムも豊富で、血圧を調整したり、健康な骨を維持したり、心臓や胃腸の健康をサポートします。



特性
脂質、コレステロール、塩分を含んでいませんが、毎日の栄養補給に役立つ食べ物です。しかし、食べ過ぎはいけません。1日におおよそ1個程度(約150g)が適量と言われています。
属性(グナ):重性
味(ラサ):甘味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
ジャガイモは新鮮なうちに食べ、長期間保存しないようにしましょう。緑色になっていたり、芽や傷があったりした場合は、食べない方が良いでしょう。
また、ポテトチップスやフライドポテトは、じゃがいもを油で揚げた時に、身体に有害な物質が発生するといわれていますので、頻繁に食べることは避けましょう。
さつまいも
Sweet potato
- 野菜
主な作用
食物繊維が豊富
さつまいもを切った時に切り口から出るミルク状の白い液体はヤラピンと呼ばれ、胃の粘膜を保護したり、腸の働きを促進したり、排便をスムーズにする作用があります。
ヤラピンは特に皮に多く含まれています。



特性
さつまいもは、ビタミンCも豊富ですが、熱に対して安定しているため焼いても蒸しても変質しません。
属性(グナ):乾性・重性・粗性
味(ラサ):甘味・渋味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
アーユルヴェーダでは、ギーとクミンなどのスパイスでオイル蒸しにするとさつまいもの旨みが凝縮されて、より美味しさを感じることができるでしょう。
できたら皮は剥かずに皮も一緒に食べると健康的です。

ニンジン
Carrot
- 野菜
主な作用
身体の若返りにニンジン
にんじんに含まれるβーカロテンは、体内でビタミンAに変換されて抗酸化作用を発揮します。さらにビタミンAは免疫細胞の働きをサポートしたり、眼病を予防したりします。
またニンジンには食物繊維や抗酸化物質も含まれ、腸内環境を整え、動脈硬化や高血圧の予防にも役立ちます。

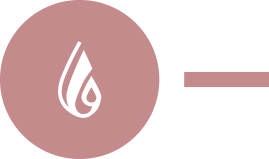

特性
ニンジンは身体を滋養し、消化を助け、血液を浄化する食品です。
ヴァータとカパを鎮静します。赤いニンジンは温性と言われています。
属性(グナ):鋭性・重性
味(ラサ):甘味・苦味・渋味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):辛味
健康ポイント
ニンジンは調理法によって作用が変わるので、蒸したりスープにしたりすると消化しやすくなりヴァータの人に適しています。
若返り効果があるので、体やお肌の健康のためにとりたい食材です。
栗
Chestnut
- 果実
主な作用
秋の体調不良を予防するためにぜひ食べておきたい旬の食材
ビタミンCが豊富に含まれているため、疲労回復や風邪予防、抗酸化作用によりシミやシワを防ぐ効果が期待できます。
疲労回復や肌の代謝を促すビタミンB1や老化防止に役立つビタミンB2 も含まれます。さらにむくみ解消や高血圧予防のカリウム、血液を作る葉酸も含まれ、腸内環境を整える食物繊維も豊富に含まれています。



特性
栗は他のナッツ類より脂質が少なく、でんぷん質が多いのが特徴です。糖質やカロリーが多いため、食べ過ぎには注が必要です。
属性(グナ):重性
味(ラサ):甘味・渋味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味・温性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
果皮が深みのあるこげ茶でツヤがある 全体に丸みがあり、重みがあるものを選びましょう。
栗の1日あたりの適量は10~15粒が目安です。子どもの場合は1日5粒を目安にしましょう。

梨
Pear
- 果実
主な作用
美容や健康のために食べたい果物
水分や食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富で美容や健康に良い果物です。カリウムを比較的多く含むため、むくみ改善やデトックス効果や、そのほかにも便秘や高血圧の改善や予防が期待できます。
梨に含まれるビタミンCやポリフェノールは老化防止にも役立ちます。



特性
ミネラルのホウ素が他のフルーツや野菜に比べて多く皮に含まれるため、女性ホルモンの働きを高め、美肌効果に繋がります。
属性(グナ):重性・乾性*・粗性
味(ラサ):甘味・渋味・酸味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):辛味*
注2:*アーユルヴェーダ医や現代研究者の考察です
健康ポイント
夜に摂取すると水分が多いため、トイレが近くなる可能性があります。
さらに重性なので、夜ではなく消化しやすい朝か昼に食べるようにしましょう。
かぶ
Tunip
- 野菜
主な作用
胃腸が疲れた時や胃もたれや胸やけ予防に
食物繊維が豊富で消化促進を促します。生でも加熱しても消化に良い効果があります。
さらにビタミンCが細胞の酸化を防ぎ、老化や病気を予防したり、免疫力を高め、風邪や感染症の予防になります。
カルシウムが豊富で、骨密度の維持に役立ちます。カリウムは余分なナトリウムと排出し、血圧を安定させます。特に葉にはβ-カロテンが豊富に含まれるので、ぜひ食べて欲しいです。
【実】



【葉】



特性
かぶは実も葉もそろぞれの特性がありますので、身体の状態に合わせて食べる部位を変えましょう。また加熱することで甘味を味わうことができます。
属性(グナ)
実:冷性・軽性・鋭性・油
葉:温性・重性・粗性・流動性
味(ラサ)
実:辛味・甘味・苦味
葉:辛味・渋味・苦味
効力(ヴィールヤ)
実:冷性 葉:温性
消化後の味(ヴィパーカ)
実:甘味 葉:辛味
健康ポイント
加熱して食べると、ヴァータの増加を抑え、消化しやすくなります。
栄養成分の類似性から、葉は小松菜と、実は大根と比べられるので、かぶの葉と実の両方を食べると一石二鳥ですね。

大根
Japanese white radish
- 野菜
主な作用
生の大根で胃腸を正常にして消化促進
デンプン分解酵素ジアスターゼが豊富なことが知られています。ジアスターゼは食物の消化を助けるため、食物繊維の整腸作用で胃の弱い人や便秘の人に効果的です。利尿作用や血圧の正常化を促すカリウムや免疫強化するビタミンCも含まれています。特に葉にはβカロテンが豊富に含まれるので、ぜひ食べて欲しいです。
ただし、熱に弱く加熱すると壊れてしまいますので、生で食べれる部位は生で食べると良いでしょう。



特性
大根は根の部分だけでなく、葉も食べられ、和食には欠かせない食材。切り干し大根や漬物など保存食としてもお馴染みです。大根の根元は甘く、根先は少し辛めなので、生で食べたり、料理して食べたりと色々な味覚を楽しめます。ヴァータの人は油と調理して食べると良いです。
属性(グナ):軽性・清澄性・冷性・すりおろしたら鋭性
味(ラサ):甘味・辛味・苦味
効力(ヴィールヤ):非温冷
消化後の味(ヴィパーカ):辛味
健康ポイント
大根の切断面が青くなっている時は、「ダイコン青変症」によるものです。収穫した数日後に大根内部に生じるものですが、食べても毒はありませんが、新鮮かどうかを見極める目安になります。できれば新鮮なものをとるようにしましょう。
また、喉や肺の炎症を和らげますので、風邪や咳の際に役立ちます。
れんこん
Rotus root
- 野菜
主な作用
粘膜保護作用で喉や胃腸の炎症を和らげる
レンコンは、食物繊維が豊富に含まれています。食物繊維は便秘や高コレステロールなどの予防に役立ちます。さらに血液浄化、炎症緩和、滋養を促す食材です。鉄分も豊富で、貧血を予防し血液循環をサポートします。また、粘膜保護作用があるため、喉や胃腸の炎症を和らげます。



特性
滋養や疲労回復のためにはよく火を通して消化しやすくすると良いでしょう。中医学では秋の養生食として適していると言われています。
属性(グナ):冷性・重性・粘着性
味(ラサ):甘味・渋味・苦味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
生はカパを悪化させるため、加熱して温かい状態で食べるのがおすすめです。スパイスを使って調理すると消化に軽くなります。ハスの種で作られたインドのポン菓子系スナック「マカナ」はスーパーフードとして話題です。
日本でもアジアン食材店で販売しているので、スパイスやギーと炒めると美味しいです。

白菜
Chinese cabbage
- 野菜
主な作用
食物繊維が腸内環境を整え、消化促進を促す
免疫力を高めるビタミンCや抗酸化作用のβカロテンが病気や老化を予防します。
さらに、血液循環を改善する鉄分が豊富です。その他にも利尿作用、抗炎症作用があります。


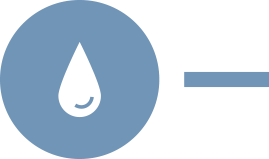
特性
白菜は身体を冷やし、炎症を抑えます。加熱調理することで消化力を高めます。
白菜から出る水分は身体が速やかに摂取できるので、茹でたり、煮たり、炒めたりして白菜の養分をたっぷりとりましょう。
属性(グナ):冷性・軽性
味(ラサ):甘味・(苦味・渋味)
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
白菜の黒い点々は、ゴマ症といわれていますが、食べても問題ありません。白菜が成長する過程でストレスを受けたときにポリフェノール類の蓄積で白菜の細胞が反応して黒い斑点が現れるようです。
里芋
Taro
- 野菜
主な作用
胃腸を整える冬のエネルギー源
でんぷんが主成分で、エネルギー源として優れています。食物繊維が豊富で、腸内環境を整え便秘を予防します。
また、粘液成分が胃腸を保護し、炎症を和らげます。

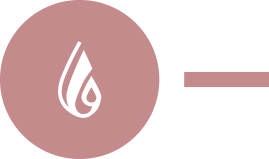

特性
里芋は滋養作用があり、体力を補う食材とされています。
冷性があるため、冷え性の人やヴァータが増加している場合は、温めて食べましょう。
属性(グナ):重性
味(ラサ):甘味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
消化が重い食材のため、過剰摂取すると消化不良を引き起こすことがありますので、スパイス(ジンジャー、クミンなど)を加えると消化をサポートできます。

長ネギ
Green onion
- 野菜
主な作用
冬場の風邪やインフルエンザ予防に
硫黄化合物(アリシン)が免疫力を高め、感染症を予防したり、血液をサラサラにし血行を改善したりします。さらに呼吸器や関節の炎症を抑えたり、ビタミンB1の吸収を助けエネルギー代謝を促進したりします。また身体を温める作用もあります。



特性
辛味によって、代謝促進が促され、冷え性や寒さによる不調を和らげます。鼻づまりや喉の不調を改善し、呼吸を楽にしたり、冷えによる筋肉の強張りを緩和したります。
抗菌作用があるため、風邪やインフルエンザを予防できるのもポイントです。
属性(グナ):鋭性・乾性
味(ラサ):辛味・甘味
効力(ヴィールヤ):温性
消化後の味(ヴィパーカ):辛味
健康ポイント
生で食べると刺激が強いので、薬味として使うことが多いです。生の長ネギの匂いを嗅ぐとカパの鎮静に役立つといわれています。
軽く加熱したり、太白ごま油で炒めたりすることで、甘味の効能が取れます。
ブロッコリー
Broccoli
- 野菜
主な作用
肥満や糖尿病、うつ病や認知症予防の食事療法に役立つ
農林水産省の「指定野菜」に2026年度から追加されるブロッコリー。スルフォラファンは抗酸化作用や抗炎症作用があり、インスリンの働きをよくするという研究発表があります。さらに脳の血管を保護する効果があり、うつ病の予防や再発防止につながる可能性があるといわれています。
記憶や学習能力をサポートするビタミンKや認知症やアルツハイマー病のリスクを低下させるカロテノイドが含まれています。



特性
アーユルヴェーダでは体内の未消化物(アーマ)を減少させ、軽いデトックス効果を持つ食材とされています。
現代医学でブロッコリーは、肥満や糖尿病、うつ病や認知症予防の食事療法に役立つ健康的な食材です。
属性(グナ):粗性*・乾性*
味(ラサ):甘味*・渋味*
効力(ヴィールヤ):冷性*
消化後の味(ヴィパーカ):辛味*
*アーユルヴェーダ医や現代研究者の考察です
健康ポイント
冷性の性質なので、蒸したり、スパイス(クミン、コリアンダーシード、ターメリック)を加えるたりして食べると消化しやすくなります。

ほうれん草
Spinach
- 野菜
主な作用
適度に食べると健康に良い食材
鉄分と葉酸が血液を増やし、疲労回復を促します。骨の強化と視力の保護に役立つ栄養素豊富です。体内の熱を抑え、消化を助ける軽い食材とされています。



特性
ほうれん草の苦味が血液を浄化し、毒素の排出を促します。冷性の性質があるため、冷え性やヴァータの人は温めて食べると良いです。
属性(グナ):粗性・乾性
味(ラサ):渋味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):辛味
健康ポイント
過剰に食べすぎるとショウ酸が多いため、尿道欠席のリスクを高める可能性がありますので、適量食べましょう。
蒸したり、茹でたり、炒めたりして温かく調理して食べると消化に良いです。
りんご
Apple
- 果物
主な作用
旬の完熟リンゴを食べて免疫ケア
食物繊維のペクチンが腸内の善玉菌を増やし、便秘や下痢を予防します。また糖の吸収を緩やかにし、血糖値を安定させます。ポリフェノールやビタミンCの抗酸化作用により免疫機能もサポートします。


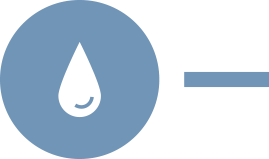
特性
完熟したりんごはピッタを鎮静させ、少量ならカパを整えます。甘味がエネルギー補給し疲労回復になります。低カロリーでありながら、満足感を得られるため、ダイエットにも最適です。
属性(グナ):軽性*・粗性*
味(ラサ):甘味*・渋味*
効力(ヴィールヤ):冷性*
消化後の味(ヴィパーカ):甘味*
*アーユルヴェーダ医や現代研究者の考察です
健康ポイント
酸味の強い未熟なりんごはピッタを増加させます。多く食べ過ぎると便が緩くなることもありますので、ほどほどに。冷性の食材なので、温めたり、スパイス(シナモンやクローブ)を加えると、生のりんごとは違った美味しさを楽しめます。

オレンジ(みかん)
Orange
- 果物
主な作用
ビタミンCが豊富で免疫力を高め、風邪予防に
クエン酸が乳酸の分解を助け、疲労感を軽減します。抗酸化作用とコラーゲン生成の助ける栄養素が肌の健康を保ちます。



特性
みかんの酸味が消化を活発化し、食欲を促します。軽い解毒作用を持つ果物とされています。
属性(グナ):重性
味(ラサ):甘味・酸味
効力(ヴィールヤ):温性
消化後の味(ヴィパーカ):甘味
健康ポイント
アーユルヴェーダではオレンジなど柑橘系果物のように酸味のある食べ物は、牛乳やヨーグルトと一緒に食べると毒になるといわれています。
特にオレンジ(みかん)は酸味が強いので空腹時や胃の不調がある時は控えましょう。
バナナ
Banana
- 果物
主な作用
糖質が豊富で、すぐにエネルギーになる食材
糖質やビタミンB6がエネルギー代謝をサポートし、疲労を軽減します。食物繊維(特にペプチン)が腸の働きを整えます、便秘や下痢を緩和します。
カリウムとマグネシウムが筋肉の収縮と緩和を助けます。



特性
バナナは栄養価が高く、身体を滋養し、潤いを与える効果があります。
滋養効果が高い反面、カパを増加させやすいので、食べる量には注意しましょう。
属性(グナ):重性・油性
味(ラサ):甘味・渋味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):酸味
健康ポイント
消化に重いので、なるべく日中に食べるようにしましょう。
消化力が弱い時は、完熟バナナを選ぶことで消化しやすくなります。消化しやすくする方法として、温かい飲み物を一緒に食べたり、スパイス(シナモン・カルダモン)を加えたりすると良いです。

ごぼう
Burdock
- 野菜
主な作用
ハーブの世界では治療に使われる薬草
食物繊維が豊富に含まれており、ごぼうの繊維は水分を大量に吸収して、便を軟らかくして便通をよくするこでとで便秘予防になります。
また、血糖値上昇の抑制や血中コレステロール値低下などにも期待できるいわれています。



特性
ごぼうは硬く、乾燥した性質を持つので、油でじっくり調理すると、消化に優しくなり、甘味も引き出します。
レーカナ(削り取る)という特殊作用があるという考察もありますので、体の中をデトックス(毒素排出)してくれる効果も期待できます。
属性(グナ):清澄性・乾性・硬性
味(ラサ):渋味・甘味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):辛味
特殊作用:レーカナ(削り取る)
健康ポイント
アーユルヴェーダでは「きんぴらごぼう」は理想的な食べ物といわれています。
ごぼうにじっくり火を通し甘辛に味付けして、よく噛んで食べましょう。
小松菜
Komatsuna
- 野菜
主な作用
体を軽くしてくれる冬に欠かせない小松菜
抗酸化作用があり、βカロテン、ビタミンC、カルシウム、葉酸などがたっぷり含まれています。独特の香りに含まれる成分には、胃もたれの解消や消化促進、咳や鼻水、痰の抑制の働きがあります。
カパを鎮めるには最適な食材です。松菜はえぐみがないため、生食もでき、消化吸収されやすい。老廃物を排出し、喘息や皮膚炎の緩和、風邪の予防、美肌効果などが期待できます。
冬に不足しがちな緑黄色野菜としてぜひ食べたい。



特性
小松菜は、炒め物や鍋、グリーンスムージーなどで使われる健康には欠かせない食材。
鉄分やカルシウム、βカロテンが豊富に含まれますが、体が軽くなるので、健康には最適です。
属性(グナ):乾性・軽性・清澄性
味(ラサ):辛味・甘味・苦味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):辛味
健康ポイント
別名「うぐいす菜」と呼ばれていた小松菜。
うぐいすが鳴き始める厳冬の終わり(春先)が小松菜を食べるのに適した季節といわれています。

春菊
Shungiku
- 野菜
主な作用
独特な香りの成分にいろいろな作用が
独特の香りに含まれる成分には、胃もたれの解消や消化促進、咳や鼻水、痰の抑制の働きがあります。
カパを鎮めるには最適な食材です。



特性
春菊は、独特な香りで好き嫌いが分かれます。
鮮度の高い春菊は、生では苦味が感じにくく、特に茎は苦味が少ないので、春菊の苦味が苦手な方は試してみてください。
サラダにして食べると、茎は歯ごたえがありシャキシャキとした食感を楽しめます。
属性(グナ):乾性・軽性
味(ラサ):苦味・辛味
効力(ヴィールヤ):冷性
消化後の味(ヴィパーカ):辛味
健康ポイント
ヴァータの人は温かいスープや油を使った料理法でバランスを取りましょう。
● ● ●
参考文献
日本アーユルヴェーダ学会・訳. チャラカ本集総論篇. 3版, せせらぎ出版, 2019, 767p, p.525-596
クリシュナ・U・K. 古典から学ぶアーユルヴェーダ. 東方出版, 2019, p214, p.200-204
NPO法人日本アーユルヴェーダ研究所. アーユルヴェーダを毎日の食卓に, 2016, p68
デイビッド・フローリー+ヴァサント・ラッド. 上馬場和夫・監訳. アーユルヴェーダのハーブ医学. 出帆新社, 2000, 436p, p.164-394
ジュディス・H・モリスン著. 本当の自分をとりもどすアーユルヴェーダ.株式会社ガイアブックス, 2023, 191p, p.132-143
オレンジページ. 素材がわかる、コツがわかる基本のお料理ブック. 第9版, 株式会社オレンジページ, 2002, 320p, p.14-104
農林水産省. 豆・麦・いも(参照2024-9-29)
厚生労働省. 自然毒のリスクプロファイル:高等植物:ジャガイモ(参照2024-9-29)
農林水産省. 野菜・果物(参照2024-11-23)