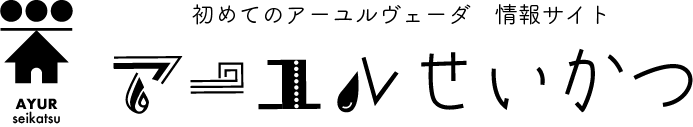猛暑の夏のアーユルヴェーダ養生法

猛暑の夏は体調管理に気をつけて
異常気象といわれることが多い最近の日本。
梅雨に入ったにもかかわらず30度を超える暑さ、そして恵みの雨が降ると思ったら、集中豪雨。自然の偉大さを痛感しています。
この時期は熱中症で救急搬送される人も多く、日頃の生活の習慣をちょっと変えるだけで快適な夏を過ごすことができます。
冷房の効いた場所と外気温にかなりの「温度差」があるため、気をつけなければなりません。
この温度差がたびたび起こると、自律神経が混乱し、体力が消耗してしまいます。その日その日の環境に合わせた養生法こそ、アーユルヴェーダが役立ちます。アーユルヴェーダを適切に取り入れることで、異常気象ともうまく付き合っていける身体になれるのです。
夏バテと熱中症について
室内と屋外の極端な温度差が原因で、徐々に体温の調整がうまくいかず、自律神経のバランスが崩れるのが夏バテです。
全身のだるさ、思考力低下、食欲不振、下痢などの症状が出ます。
一方、熱中症は、夏バテがひどくなった状態で、高温多湿が原因の発汗による脱水症状と体温の上昇になります。
夏バテの症状に加えて、めまい、吐き気・嘔吐、頭痛などの症状がプラスされます。
屋外はもちろん、室内でも何もしていない時でも発症します。
高齢者の方は、温度に対する感覚が弱くなっているため、室内でも気づかぬうちに熱中症を発症しているケースが多いようです。なるべく涼しい環境で過ごし、早め早めのこまめな水分補給が大切です。
高齢化社会の日本において、家族や周りの方も協力し合って、高齢者の健康はぜひ守っていきたいですね。
夏のドーシャ
夏はピッタドーシャが、太陽の強い日差しや高い気温や湿度によって過剰になります。
暑さをしのぐために、冷たい食べ物や飲み物ばかりをとりすぎてしまうと、ピッタが悪化して、さまざまな症状を引き起こします。
ピッタは主に消化器系や皮膚に異常があらわれますので、日頃から注意が必要です。
暑い日が続くとはいえ、なるべく冷たいものは避けて過ごすことがアーユルヴェーダでは大切です。
また、暑すぎる日は日中はなるべく外出せず、少し涼しい早朝くや夜に外出するほうが良いでしょう。
夏によくみられる症状
夏バテや熱中症です。体内に熱がこもってしまい、知らぬ間に重症化してしまうケースもあるので気をつけなくてはいけません。
また、ついつい冷たいものを多くとってしまうため、胃腸の働きが悪くなり、下痢など消化器系のトラブルが起こりやすいです。
さらに、皮膚や眼のトラブルも起きやすいので、直射日光はなるべく避けたいものです。
体と心の不調
痛みや体のだるさを感じやすい
- 体内に熱がこもる
- 体のだるさ
- 疲れがとれない
- 食欲不振
- 体重減量
- 下痢
- 皮膚に湿疹
- 乾燥肌
- 眠れない
- 憂うつ


夏に取り入れたい生活処方
日常生活を少し変えてみるだけで、夏を元気に乗り切ることが可能になります。規則正しい生活やバランスの良い食事、適度な運動に加えて、下記内容をぜひ試してみてください。
METHOD
01
適切な水分をとる
早め早めに水分をとることが大切です。
できたら、十分に沸騰させた湯冷しを飲みましょう。
体内の熱を鎮めるコリアンダーウォーターや麦茶などもおすすめです。

METHOD
02
外出時には日傘・帽子・サングラス
夏の強い日差しは、眼やお肌から刺激を受けてピッタを悪化させます。できる限り露出しないようにアイテムを活用しましょう。

METHOD
03
旬の苦味・渋味・甘味のある野菜をとる
夏はさまざまな夏野菜が美味しい季節。特に瓜科の野菜や苦味や渋味のある野菜を食べると良いでしょう。せいろを使ってせいろ蒸しすると簡単ですぐにできるのでオススメです。

METHOD
04
暑さを鎮静するアイテムを有効活用
アーユルヴェーダでは暑さを鎮静するものとして、ローズウォーター、ココナッツオイル、ギーがあります。ローズウォーター化粧水にしたり、オイルマッサージは夏はココナッツオイルを使ったり、料理にギーを使ったりしてみましょう。

CAUTION
!
避けるべき夏の生活処方
冷たい飲食物やアルコールはなるべく避けること。
アイスやかき氷、氷はなるべく避けましょう。
食べているときは幸せでも、後に消化不良になる可能性がありますので、習慣化することはやめてください。
また、イライラしやすいので、なるべく穏やかに過ごすように意識しましょう。
夏に取り入れたい
食材・スパイス
夏はクールダウンするような食材やスパイスはもちろん、消化にも優しいものを取り入れたいですね。
また、苦味・渋味・甘味のあるものをとって、過剰なピッタを鎮静させたいです。
具体的な料理をあげると、ゴーヤチャンプル、葉野菜の蒸しもの、煮物、豚肉の生姜焼き、キチャリ(インドの伝統的なお粥)、ムング豆ご飯などがお勧めです。
● ● ●
参考文献
日本アーユルヴェーダ学会・訳. チャラカ本集総論篇. 3版, せせらぎ出版, 2019, 767p, p.126-127
クリシュナ・U・K. 古典から学ぶアーユルヴェーダ. 東方出版, 2019, p214, p.77-80