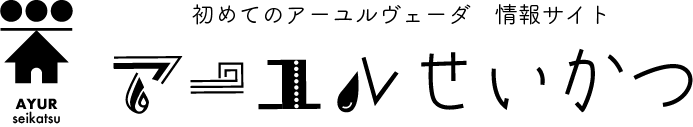アーユルヴェーダで快適に春を過ごそう

春とは
アーユルヴェーダの春は、徐々に暖かくなる3月後半から5月初めの時期をいいます。
冬の間に蓄積していたカパ・ドーシャが春の日差しで溶け出すため、カパが悪化し、冬に比べると消化力が弱まってくるというのが特徴です。
花粉症などのアレルギー症状が出るのも、消化力が弱まり、アーマ(未消化物)が影響していると考えます。
春の花を楽しむことも推奨しています。
春のドーシャの傾向
春は「カパ(水)」が悪化する季節です。
冬の間に溜まったカパ・ドーシャの量によって、春の体調は左右されます。多いほど悪化します。
カパの悪化により、消化の火がバランスを崩し、アーマ(未消化物)が体の弱い部分に定着します。
アレルゲンがこの定着した弱い部分に触れると、不耐性が起こり、このアレルゲンを拒否することで、アレルギー反応が起こります。花粉がアレルゲンの場合、花粉症を発症します。
いかにカパを悪化させずに、消化力を維持させることでアーマ(未消化物)を生まないようににすることが大切です。
春に起こりやすい症状
春に多くみられる症状は、カパの影響が大きく、消化の火が弱まるため、状況に合わせた食生活を取ることが大切です。
よくみられる症状は、鼻水・鼻づまりを代表とする花粉症といったアレルギー症状です。消化がうまくいかず、アーマ(未消化物)があるとアレルギー症状が現れるといわれています。
他にもカパ特有の症状である倦怠感・眠気・だるさや、むくみや水分代謝の低下が見られます。
冬に比べてアグニの火(消化の火)が弱まるため、消化力を気にするこ大切です。
体と心の不調
花粉症に伴う体調不調で
気持ちも凹みやすく
- 花粉症
- 頭痛・頭重
- 鼻水・鼻づまり
- 目のかゆみ・涙目
- 喉のかゆみ・咳
- 消化力の低下・食欲不振
- アレルギー性皮膚のかゆみ
- 肩や腰のこり
- 蕁麻疹
- 肝機能の乱れ


春に取り入れたい生活処方
この時期は、体を適度に動かし、消化力を低下させないようにし、さらにアーマ(未消化物)を体に溜めないことが重要です。春は憂鬱な気分になりやすいので、気分もリフレッシュさせることもポイント。春に効果的なアーユルヴェーダの健康対策を紹介します。
METHOD
01
毎朝6時前に起きる
カパの時間(午前6時〜10時)の前に起きることが大切です。
日の出の96分前に起きるのがベストですが、まずは6時までに起きることを習慣化することから行ってみましょう。

METHOD
02
活動的な生活を
室内でできる運動で構わないので、少し汗をかくくらいの適度な運動をするようにしましょう。
ジムやヨガ、ストレッチなどで体を動かすと体内の余分な水分や老廃物(マラ)を排出させるので、体も軽くスッキリします。
エレベーターを使わずに階段を使うなどちょっとした工夫でも良いでしょう。

METHOD
03
一日中、白湯を飲む
体の中のアーマ(未消化物)をなるべく少なくすることで花粉症などのアレルギー症状を軽減できるので、一日中白湯を飲みましょう。
白湯は一番身近な天然のお薬です。

METHOD
04
ガルシャナ&オイルマッサージ
絹の手袋でシャカシャカと皮膚を擦るドライマッサージ(乾布マッサージ)はガルシャナといい、血行を良くし、カパを減少させます。オイルマッサージをその後に行うと、健康増進や美容のためには良いとアーユルヴェーダではいわれています。

CAUTION
!
避けるべき春の生活処方
この時期は運動不足だったり、昼寝をしたりすると、カパが悪化して体調不良を感じやすくなります。
また、太陽に当たりすぎも良くありません。
消化力には注意したほうが良い季節です。
冷性や重性、脂肪分の多い食べ物は控えましょう。
消化に重いものばかり食べているとアーマ(未消化物)を蓄積させますので注意しましょう。
刺身、生野菜、冷凍食品、缶詰などは控えましょう。
春に取り入れたい
食材・スパイス
春は消化を促進する食材やスパイスを使うことが大切です。
カパを鎮静するような作用のある食材やスパイスを取り入れたいですね。
カパを鎮静させるために、辛味・苦味・渋味、温性・軽性のあるものをとりましょう。
具体的な料理をあげると、野菜や肉のスープ、キチャリ(ムング豆のお粥)など、食材やスパイスの効能を上手に取り入れましょう。
● ● ●
参考文献
日本アーユルヴェーダ学会・訳. チャラカ本集総論篇. 3版, せせらぎ出版, 2019, 767p, p.122-124
クリシュナ・U・K. 古典から学ぶアーユルヴェーダ. 東方出版, 2019, p214, p.83-88