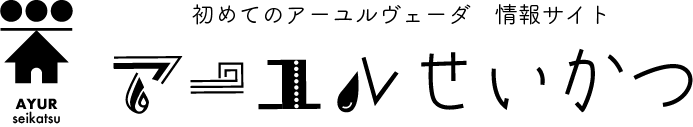病は食から、だから六味のバランスを大切に

六味とは
アーユルヴェーダは、人間の健康と生命活動は「ドーシャ(体質)」によって左右されるとされます。
そして、食養生の基本となるのが6つの味「甘味・酸味・塩味・辛味・苦味・渋味」、つまり「六味」です。
これらは味覚的な要素に留まらず、それぞれが人体の構成要素や機能、そして精神状態にまで影響を与えるとされ、バランスをとることが健康を維持する秘訣と考えられます。
まさにアーユルヴェーダがキッチンファーマシー『台所薬局』といわれる所以です。
アーユルヴェーダが根付いているインドやスリランカでは、体の調子が良くないと感じた時は、まずは食事療法を試すことが習慣化されています。家庭では、家族の体調に合わせて六味のバランスを調整しながら料理をして食べることが当たり前に行われています。
ドーシャ(体質)と六味は心と体の健康のために、ぜひ知って欲しいと思います。日本の食事にも取り入れられる知恵です。
六味の特徴と主な食品一覧
それでは具体的に六味についてみていきましょう。
| 味 | 食品 | 味の効果 |
| 甘味 | 米、小麦などの穀物、ナッツ類、牛乳などの乳製品 バターなどの油脂類、肉、魚、はちみつ、砂糖 甘い果物、甘い野菜 | 滋養強壮 組織の修復 疲労回復 |
| 酸味 | 酢、レモン、グレープフルーツなどの酸っぱい果物 | 消化促進 コラーゲン生成 |
| 塩味 | 塩、しょっぱい加工品 | 水分保持 消化・吸収の促進 |
| 苦味 | ゴーヤ、ナス、春菊、レタスなどの緑黄色野菜 ターメリック、アロエベラ | 血行促進 解毒 |
| 辛味 | 生姜、唐辛子、コショウ、クミン マスタードなどのスパイス類 | 解毒 抗炎症 胃腸の清浄化 |
| 渋味 | 豆類、緑茶、山菜、たけのこ、葉野菜、緑黄色野菜 | 収れん 止血 炎症抑制 |

ポイント♪
旬の食材はその季節の味を多く含んでいることが多いため、旬の食材をとりいれると簡単です。健康のためには自然の恩みは本当に大切ですね。
六味とドーシャの関係
六味はドーシャとの結びつきが深いとされます。
ドーシャの状態によって取り入れる味のバランスを調整することで、体調を整えます。
つまり、普段の料理で体調に合わせた食品を使いながら、健康維持を保つ工夫がされているのです。
家庭で毎日できるセルフケアなのです。
暮らしへの取り入れ方
1. 日々の食事で味のバランスを意識する
食事は六味をバランスよく取ることが大切です。
六味をバランスよく取り入れることで心も体も満足感が高まります。
食材の美味しさを味わいながら、よく噛んで食べるとより良いでしょう。
2. 季節や体調に合わせて調節
季節や体調によって六味のバランスを変えることで、体調を整えることが可能です。
六味の効果から最適な食材を使って料理すると良いですね。
春:渋味・苦味・辛味を少し多くとる
梅雨・台風:食事で酸味・塩味の強いもの、油脂類をとる
夏:甘味、消化しやすい食べ物、ひんやりとした食べ物をとる
秋:苦味・甘味・渋味を少し多くとる
冬:甘味・酸味・塩味を少し多くとる
3. 味の過剰・欠乏に注意
一つの味を取りすぎたり、取らなかったりは六味のバランスを崩すため、体調には悪影響を及ぼす可能性があります。
例えば、甘味をとりすぎるとカパが増えて肥満傾向に、酸味ばかりだとピッタが増えて化膿しやすくなります。渋味や辛味を取りすぎるとヴァータが増えて体が乾燥してしまいます。
各味は適度に、そして全体のバランスが大切です。
現代にも通じる「六味」の智慧
アーユルヴェーダの「六味」は、日本の「五味(甘味・酸味・塩味・苦味・辛味)」とも重なる部分があります。さらに素材の味を生かす「淡味」を加えたものを「六味」といわれます。
すなわち、「多様な味=栄養素バランス」として、これらの味がバランスよく含まれることで、料理はより美味しく、飽きずに食べられるとされています。
アーユルヴェーダの六味には、それぞれの味には明確な作用があり、ドーシャとのバランスが全ての鍵。
毎日の食事にほんの少し意識を向けるだけで、古代インドの智慧が現代にも豊かな調和と健康をもたらしてくれることでしょう。
● ● ●
参考文献
日本アーユルヴェーダ学会・訳. チャラカ本集総論篇. 3版, せせらぎ出版, 2019, 767p