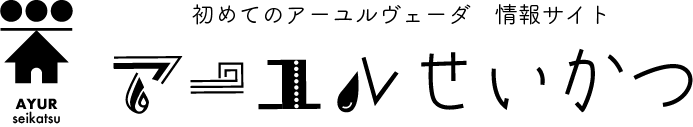備蓄米をきっかけに「消化に軽いお米(古米)」をアーユルヴェーダで知ろう

備蓄米とアーユルヴェーダの親和性
最近、日本各地で「備蓄米」に関するニュースが増えています。
自然災害や凶作などによって市場価格が高騰することを抑え、食料の安定供給や食料価格の安定化といった国民の食料を安全保障する対策として備蓄されています。だから自治体や企業が一定期間保管していたお米を市場に出すことで、古米(保存されていたお米)が市場に出回る機会が増えつつあります。この動きは、実はアーユルヴェーダの知恵と非常に親和性があります。
アーユルヴェーダでは、新米よりも古米(1年以上寝かせたお米)を推奨しています。これは、消化力(アグニ)を重視するアーユルヴェーダならではの考え方に基づいています。
では、なぜ古米の方が身体に優しいのでしょうか?
その理由を、アーユルヴェーダの視点と科学的な側面の両面から紐解いていきます。
アーユルヴェーダにおける「米」の捉え方
アーユルヴェーダは、五千年の歴史を持つインドの伝統医学で、健康の基盤として「食べ物の消化力(アグニ)」を重視します。
だからどれだけ栄養価の高い食べ物でも、それがきちんと消化・吸収されなければ体の力にはならないというのが基本的な考え方です。
そのため、食材選びの際には「消化に軽い」か、「重い」かが重要な指標の一つとなります。
アーユルヴェーダでは、「1年以上熟成された米は軽く、消化に良い」といわれています。これが古米に該当します。


新米と古米の違いとは
上記のように、新米と古米では水分含有量や成分の変化により、食感や風味、消化性に違いが生じます。
| 新米 | 古米 | |
| 定義 | 収穫年の年末までに精米・包装された米 | 収穫後1年以上経過した米 |
| 水分含有量 | 高め(約15.5%) | 時間の経過とともに減少し、13~14%程度になる傾向 |
| たんぱく質含有量 | やや低め(約7.4%) | 保管中の変化により若干増加する可能性あり |
| アミロース含有量 | 品種により異なるが、一般的に低めで粘りが強い | 時間の経過とともに増加し、粘りが少なくなる傾向 |
| 脂肪酸値 | 低め(新鮮な状態) | 保管中に脂質が分解され脂肪酸が増加し、風味に影響を与える |
| 食感 | 柔らかく、粘りがあり、香りが良い | 硬く、粘りが少なく、古米特有の香りがある |
| 消化力 | 粘り気があり、消化に重いとされる | 乾燥しており、消化に軽いとされる |
水分量と構造
新米は収穫後間もないため、水分含有量が高く(約15〜16%)、その結果、炊き上がりがふっくら・もっちりとした食感になります。これは日本人にとって「おいしいお米」の象徴でもあります。
一方、古米は時間の経過とともに水分が抜け、でんぷん質が締まり、炊き上がりはややパサっとした食感になります。水分量は13〜14%程度。しかし、アーユルヴェーダでは、この乾燥度の高さが「消化に軽い」とされる理由の一つです。
消化への影響
新米は水分が多く、甘みや粘り気がある分、体内での分解・吸収に時間がかかりやすく、「カパ(粘性・重さ)」を増やすとされます。そのため、消化力が弱っている人や、胃腸に負担をかけたくないときには不向きです。
一方、古米は余計な水分や粘性が抜けており、よりシンプルな構造になっているため、アグニ(消化力)に負担をかけず、軽やかに消化されやすいとされています。
消化に軽いお米の選び方
✔️1年以上経過した日本の古米(備蓄米含む)
備蓄用に保管されていた古米は、まさにアーユルヴェーダが推奨する日本のお米といえるでしょう。一般には「味が落ちる」「食感が劣る」と敬遠されがちですが、体に優しいお米として見直す価値があります。
✔️インドやパキスタンの「バスマティライス」
アーユルヴェーダでも特に評価が高いのが、インディカ米(長粒米)に属するバスマティライス。
長く細長い粒で香り高く、粘りが少ないため、カパやピッタを増やしにくく、消化に極めて軽いとされます。
食後の重さや眠気を感じにくく、インドのおかゆ「キチュリ」はデトックス期間や断食後の回復食に適しているといわれています。
日常に取り入れるための工夫
消化に軽いとはいえ、古米やバスマティライスは新米に比べて「味気ない」「パサつく」と感じることもあります。だからそんな時は、アーユルヴェーダの智慧を活かした調理法を取り入れるのがおすすめです。
ギー(精製バター)を少量加える:消化を助け、風味も豊かに
ダル(豆スープ)やスープと一緒に:水分と一緒にとることで吸収がスムーズに。
クミンやターメリックを一緒に炊く:アグニを高めるスパイスで軽さをさらにアップ。
「身体に軽いお米」を体験するチャンス
備蓄米の活用が注目される今こそ、「味よりも身体への負担の軽さ」に目を向けるよい機会かもしれません。
アーユルヴェーダでは、季節や体調によってお米の選び方を変えることも自然なこととされています。
食べ物を「美味しいかどうか」だけでなく、「身体がどう感じるか」という視点で捉えると、日々の食卓がより豊かになります。
私たちは日々、「おいしい」を追い求めるあまり、時として「身体に優しい」を見落としてしまいがちです。
しかし、アーユルヴェーダが教えてくれるのは、「消化できてはじめて栄養になる」という根本の真理。
新米の季節の楽しみももちろん大切にしながら、時には古米やバスマティライスといった“消化に軽いお米”にも意識を向けてみてはいかがでしょうか?
備蓄米のニュースをきっかけに、そんな視点が広がることを願っています。
● ● ●